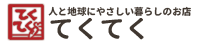明治時代に導入されて日本で改良された元祖西洋栗かぼちゃ。ホクホクして煮物がうまい。
東京カボチャの特徴
明治時代西洋かぼちゃが入り、日本風に改良された品種です。
耐病性が強く作りやすいので家庭菜園向きです。
果皮は灰緑色で果重は1.3kgくらい
果肉は濃黄色で厚肉、栄養価も高く食味最高です。

東京カボチャの栽培方法
カボチャは連作に強く低湿地を嫌うので水はけのよい畑の土手などが最適です。
西洋カボチャは果菜類の中でも特に低温に強く10度以上あれば生育できるので直播きをおすすめします。
トウモロコシとの混植はコンパニオンプランツの最適種です。
カボチャは少しくらい未熟な堆肥でも大丈夫です。
食生育がうまくいくと育ちが良くなりますので初肥はしっかり与えます。
ただしあまり肥料分が多いとツルや葉ばかり茂り、雌花が落ちてしまいます。
そうなると実付きが悪くなりますので、加減が難しいところです。
カボチャは蔓の下に浅く広く根を張るので株間はしっかりとって
乾燥や多湿を避けるように熱めの草マルチやわらなどを敷くといいでしょう。
家庭菜園においては、つるは摘芯や芽かきをせずにどんどん伸ばします。
つるを土からはがして移動させることは根にダメージを与えるので厳禁です。
東京カボチャはチョウや蜂が多いところでは人工授粉の必要はありません。
ただし他家受粉なので1本植えせずに必ず2株以上を近くに植えます。
実をつけ始めると実に養分が集中して葉っぱの勢いが落ちてきます。
まわりに草が茂ってきますが、その草は身の日焼けを防ぎ地表の温度を下げてくれます。
まわりの鳥などからも実を隠してくれるので、できることなら周囲の草はあまり刈らないほうがいいです。
実をつけ始めると草勢が落ちて、葉の表面に白い粉をふいてきます。
いわゆるうどんこ病ですが、あまり広がらないようなら気にせず
広がってくるようでしたら夕方葉っぱにストチュウ水をかけて洗い流してあげます。
収穫は開花を記録しておいて、40~45日後に収穫するのが一番リスクがありません。
果皮が濃くなっていわゆるかぼちゃらしい色になりヘタがコルク状になってきたころが収穫適期です。
在来種である東京カボチャは実の大きさは均一ではなくばらつきがあります。
収穫後すぐに食べずに1カ月くらい置いておくと追熟して甘くなります。

在来種かぼちゃの種取り
ウリ科の野菜の中でかぼちゃは一番簡単ですので気楽に挑戦してみてください。
良く熟して食べておいしかったカボチャの種をとっておきます。
ワタを取って良く水洗いしてきれいにします。
よくふくらんで色の濃いものを選別します。
一週間ほど陰干しますが、色が変わってきそうなら少し早めに切り上げます。
その後乾燥剤を入れた茶筒等で保冷所に保管します。